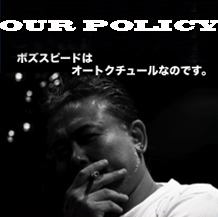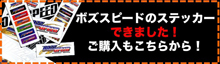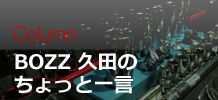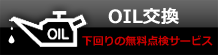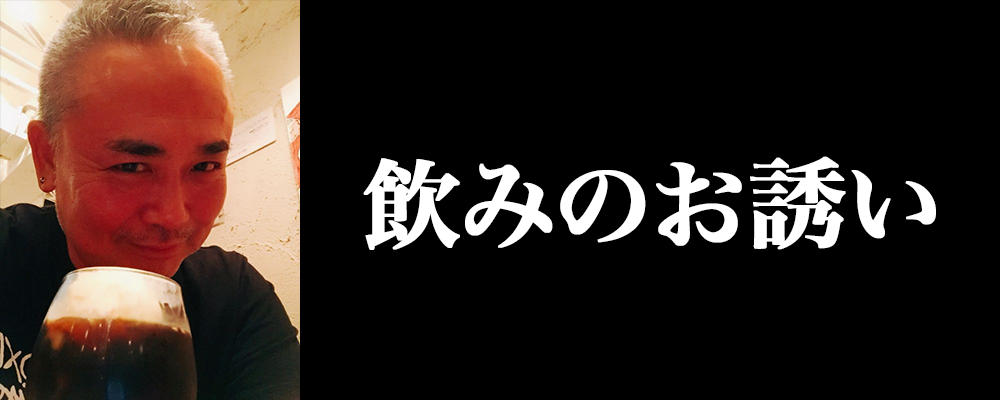2023-0910号 昭和のクルマはこんなだった!のお話
BOZZ SPEEDが発行するメルマガ
「BOZZレター」の新着記事をお届けします。
ボズレター2023-0910号 BOZZ LETTER Ver. 2023-0910
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ランエボとインプレッサのチューニングとトラブル解決なら!
もちろん軽自動車もハチロクもスポーツならなんでもおまかせ!
BOZZSPEED/ボズスピードのメールマガジン=ボズレター
2023年09月10日号
ウエブサイト https://www.bozz.co.jp/
お問い合わせ info@bozz.co.jp または 048-952-8586
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さんこんばんは!
一昨日は台風直撃とのことで、かなりビクビクしておりましたが…ボズスピードでは何事もなく胸をなでおろしております。暴風で何かが飛んできてお客様の車両に直撃とか…冗談ではないです…皆様も無事であることを祈ります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎昭和のクルマはこんなだった!のお話
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、先日何気なくテレビを見ていたところ、“昭和ってこんな時代だった” 的な番組が流れていました。内容的にはまぁ、どうでもいいようなことばかりで…デパートの屋上にはアドバルーンが浮かんでいたとか、男性はシャツをパンツの中にインするのが普通だったとか、ツッパリ(今で言うところのヤンキーですね)のカバンが薄かったとか…くっだらねえ…とか思って見ていたのですが…そのときに昭和のクルマ…というものをうっすらと考えていたのです。きっとアドバルーンくらい、今のクルマ好きさんたちから見たら異様なものなのだろうなぁ…と。
というわけで、今回は久田の思い出話。昭和のクルマはこんなだった! 的な話をお送りします。N山からアドバルーンと同じくらいどうでもいい! とか言われるのは覚悟の上です。とにかく書いちゃいます。
まず、皆さんはエンジンを始動するとき、キーをひねる、もしくはボタンを押せば普通にかかると思っている方がほとんどでしょうが…昔はちょっとした儀式が必要だったのです。まず、“チョーク” 。これはなんぞやとお思いになるでしょうが…キャブに入る空気を絞ることによって混合気を濃くするための装置なのです。まず、チョークを引き、セルを回してエンジンが始動したら、温まったことを見計らってチョークをゆっくりと戻していくのです。エンジンかけて即スタートなんて考えられません。嫌でも暖機運転をきちんとする必要があったのですね。ソレックスなどで軽くチューニングされたクルマの場合は、キーをオンにして、燃料ポンプがしばらく動作するのを音で確認し、それからアクセルを数回煽って、神様に祈りながらセルを回す…という儀式が必要でした。そこでプラグをかぶらせると“ヘボ”と罵られることは覚悟しなければなりません。まぁ、エンジン始動だけでちょっとした試練…でもありましたね。
若い久田はクルマを購入すると…まずすぐにやったのはヘッドライトの交換です。ここで「あー、ハロゲンバルブね、知ってる」なんて思った人は大甘です。バルブではなく、ヘッドライトそのものを交換するのです。車種にもよるのですが、ちょいと古めの車両ですと、ヘッドライトにバルブなんてものは存在しません。シールドビームと言いまして、ヘッドライトそのものが巨大な電球(つまり分解できません)だったのです。そしてシールドビームは圧倒的に暗い…とにかく暗い…こんなんで峠なんか行けるかっ! というくらいに暗いのです。
そこでハロゲンヘッドライトバルブが使えるヘッドライトユニットを買ってくるのです。当時のクルマは、規格サイズのヘッドライトであることが多く、ほとんどが、丸2灯、丸4灯、角2灯、角4灯の規格サイズだったのです。皆さんのよくご存知の車両でいうなら、初代86のトレノは角2灯ですね。メーカーとしては、シビエ、マーシャル、ルーカスなどの海外製がほとんどでした。ヘッドライトユニットを交換し、バルブをハロゲンに替え、そのままですとヒューズがぶっ飛びますのでリレーユニットを組み込んで、やっと何とかまともなヘッドライトになったのです。もちろん、それでも現代のクルマのヘッドライトに比べたら…笑っちゃうくらい暗いのですけど。
そんな時代でも、サスもやっぱりいじりたい…しかし、車高調整なんてものは存在しません。いや、あったかもしれませんが、街道レーサー(この言葉が死語ですねえ)にとってはイメージすら出来なかったですね…てか、そもそも、リアサスが板バネのサニーとか、車高調整式無理だし。
でまぁ、無難な方法としてはショックアブソーバーだけを交換。とこうなります。俺のはコニだカヤバだとわぁわぁ言っていた小僧がたくさんいたのです。当時は、減衰力を調整できるショックは殆どなかったのですが…じつは裏技がありまして…コニのスペシャルDというショックは、ヘタってきたときに減衰を復活させるために、ロッドを一番深くまで押し込んで、時計回りに回すと硬くなる…という機能がありました。これは4回できるのですが…新品の時から4ノッチ回してしまうのです。ガチガチのスペシャルDのスペシャルの完成です。ほんと…小僧ってろくなことしませんね…
ショックアブソーバーだけの交換では飽き足らず、車高を下げたい…と考えると今度はバネ交換なのですが、ショックのストロークが長いままで短いバネを組み込むと…はい、伸びたときにバネが遊びます。下手すると外れます。怖いですね…久田は耐久レースのフォーメーションラップでバネが外れたことがあります。そのときは怪力メカニックが腕力でバネを縮めて無理やり組み込む…という技をスターティンググリッドでやってくれました。すげえ…
そのうち、“遊ばないのに車高が下がる、バネレートは硬くなる” なんて魔法のようなバネを売り出すメーカーが出てきました。はい、インチキです。なことできるわけ無いじゃん。ノーマルより柔らかいバネでしたね。
強化ブッシュにするといいらしい…なんて噂を聞くと交換してみたくなるのですが、そもそも売っていません。売っていたのかもしれませんが、当時の久田は知りません。ネットなんて便利なものもありません。カーボーイという自動車いじりの雑誌が発売され、穴のあくほど読んだ覚えがあります。ちなみに、久田。カーボーイの創刊2号に出てます。当時の愛車の117クーペのクラッチ交換やってますね。カーリーの長髪で…
さて、ブッシュですが、強化ブッシュにしてみたい。でもない。さぁ、どうする…と、ここで登場するのはトンカチと五寸釘です。なんと…ブッシュに五寸釘打ち込んじゃうでしょう! ゴムを打ち込まれた釘で押すことによって硬度アップ!! バカだと思うでしょ? 信じられないでしょう? でもやってたの。ちなみにこの釘作戦。なんと驚けマツダの開発部門でも同じことしていたというのであながち間違いでもないのかもですね。もちろん、よいこの皆さんは絶対に真似しないように。
次にブレーキです。スポーツパッドなんてものは…ほぼフェロードしかありません。一択です。それもDS11というパッドしか選びようがなかった記憶があります。このDS11、組んでそのまま走る…なんてことが出来ません。一度組み付け。左足でブレーキを踏みながら走ります…そのうちにブレーキパッドからもくもくと煙が出て、挙げ句には燃えだします。その炎を、走行風で消して、ゆっくり走ってパッドとローターを冷やします。そしてガレージに帰り、パッドを外して、表面の炭化した被膜をサンドペーパーで削ります。ローターも削ります。もう一度パッドを組み込み、フルード交換して完成です。たかがパッド交換にこんな手間がかかったのです…信じられますか?
とまあ、色々と無茶苦茶な時代だったのですが、あれはあれで楽しかったですね。でも、あの時代に比べると今はなんと素晴らしい時代なのでしょうねえ。エンジンは普通にかかるし、サスは色々選べるし、パーツも豊富にあります。性能的にも桁が違う…というくらいに良くなっています。よく、“昔は良かった” なんて話をするジジィがいますが…クルマに関して言えば、今の方が全然いいです。性能的にも、安全性に関しても、信頼性に関しても。ただ、どんな時代であれ、最終的に安全を左右するのは人間です。さらにいうと、性能が上がり、走行ペースが上がったぶんだけ、何かあったときの危険は大きいとさえ言えます。くれぐれも事故を起こさぬように、安全運転を心がけてくださいね。
さてアムクレイド走行会ですが、Bクラスは満員御礼ですが、AとCにはまだ若干の空きがあります。参加希望の方はお早めに久田に連絡ください。
それではまた次号で!!
BOZZ SPEED/ボズスピード
URL:https://www.bozz.co.jp
メール:info@bozz.co.jp